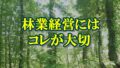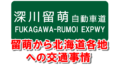弊社は、山林から搬出される丸太の生産販売をしています。
山林は不動産で土地なので買取できませんが、立木の状態で価格をつけて買取しております。
そこに生育する立木のみを買取しております。
山林売買は土地取引です。
立木売買は動産取引で不動産売買とは異なります。

山ごと引き取ってほしい…
そんなご要望もときどきあります。
山林売買と立木売買の違いについて解説いたします。
山林を売るのは林業経営を売ること

林業経営は山林不動産を所有し、50年、100年と長期にわたる計画と投資が必要です。
林業も投資事業なのです。
植えてから収穫することでリターンを得る業種です。
北海道十勝で数千haの広大な山林を持ち、林業経営されてる方が多く存在します。
立木から丸太へ

林業収入は立木を販売して得られます。
良い立木をたくさん作ることが収益を上げるコツとなります。
植栽密度や樹種、植え方などは、長年、研究された蓄積が国や行政の森林機関にあります。
今、伐採される立木は過去の投資の結果です。
林業経営は丸太の売却結果で評価され、生産山林の価値はそれで決まります。
素材生産コスト

立木から丸太にすることを素材生産と言われます。
丸太に加工する仕事です。
いわゆる「生産コスト」になります。
いくら素晴らしい立木があっても素材生産コストが高額過ぎると利益は出ません。
きりたった山頂に高価値の立木があっても、コストがかかり過ぎて伐り出せないのです。
林業経営では生産コストである「素材生産費用」を常に考えなければなりません。
運搬コストも
素材生産の次にコストがかかるのが運搬です。
それはいくつかあります。
- 作業員を運ぶ
- 倒した木を運ぶ
- 丸太集積所から顧客へ運ぶ
伐り出す作業員や重機が入りにくい山林は作業道を新設しなければ作業開始できません。
伐倒した木を丸太集積所まで運ぶ作業道が必要です。
さらに丸太集積所から製材工場などへ運搬しなければなりません。
とにかく丸太は運ぶのにコストがかかります。
急斜面や除雪があるとさらに費用がかかります。
山林を売るということ
「土地ごと山林を売る」ということは林業経営も売ることになります。
会社の売買と似ています。
黒字の会社と赤字の会社では値段が違います。
林業についても同じです。
山林の収支がいつも良好でいつ伐採しても黒字がでる山林は高値が付くでしょう。
しかし、伐り出すたびに赤字で、手を付けられない山林は買手が現れにくいです。
林業経営価値とは所有する山林の総合価値ともいえるのではないでしょうか?
立木を売るのは林業事業

植林して育てた立木を売るのは、林業経営の通常取引です。
山林売買とは違い林業収益を得るための事業取引です。
立木の価値はコストを引いてはじき出されます。
高い売価で低いコストだと利益が増大します。
「安く作って高く売る」のが事業の鉄則なのは林業も一緒です。
しかし、日本の山林の現実はその逆がほとんどです。
立木を売るということ
立木を売却するまでのプロセスは次のとおりです。
- 植林
- 育林
- 間伐
- 主伐(皆伐)
立木を売るということは3の間伐と4の主伐で収益を得ることです。
その収益の一部を1植林、2育林にまわして投資するのが林業経営です。
収穫である立木を売ることは林業経営に欠かせないのです。
立木売却で収益を大きくしていくことが林業経営の肝になります。
50年サイクル

植林から伐採まで早い方が単位山林面積あたりの売上が上がります。
伐採まで待っていられないので、植林の木は縄文杉のように1000年育つ樹種を植えません。
植える密度、地形、気候、苗木種などによりますが、十勝だとカラマツは50年程度で成長が止まります。
収穫期がありそれ以上放置しても成長が見込めません。
どの植林木にも数十年の植林伐採サイクルがあります。
地域に合ったサイクルの樹種を選んで植栽されています。
悪い状態の立木

植えてても間伐してない山林や、台風や強風で立木が倒れたままの風倒被害の山林が放置されてます。
未間伐の細木は引き取り手が少なく安価な燃料材にしかなりません。
細いのでなかなか材積が上がらず、素材生産コストもかかってしまいます。
風倒木は「かかり木」が多く伐採が危険です。
それだけ養生するのにコストがかかります。
倒れて地面に転がっている木はだいたい腐朽していて、木材価値がつけられません。
植えたはいいものの、長年、放置された山林の立木価値はあまり良好なことがありません。
意味が違う、立木と山林の売買

立木を売ることは林業事業の一環です。
山林を売ることは林業経営を手放すことです。
似た取引のように思えますが、まったく意味が異なります。
外国人が買っている?

外国人が山林を買いあさっている…
けっこう話題になっています。
山林売買の仲介に入ることが無いので、私たちはあまり実感がありません。
ただ、特定の会社(法人)が山林を買っているというのは耳にしたことがあります。
目的が太陽光発電用なのか、節税なのか、水源のことなのかサッパリわかりません。
何となく法人と聞くと、実質支配者が外国人のことが多かったりします。
今回記事の観点から、彼らは林業経営にのりだしていると言えるでしょう。
やるかどうかは別として立木売買の収入は彼らに入るのです。
山林を売りたい
山林を売りたい人は増えてる感じがします。
2024年4月から相続登記の申請が義務化され、山林も土地なので対象に入ります。
登記するには境界線を確定しなければなりません。
境界未確定の山林が相当数あり、測量には費用がかかります。

お金がかかるなら売っちゃおう…
このところ山林売買の相談が多くなってきた理由かもしれません。
立木売買で利益を
立木の売買は林業収益です。

安定的に収益を得られる山林は日本でどれくらいあるのか?
調べましたがわかりやすい統計はありませんでした。
恐らく少ないでしょう。
急斜面が多く搬出費がかさみ、山間部からの運送コストもかかります。
北海道の一部は十分に山林収益が見込める山林もあります。
材質に欠点が少なくて緩斜面で成長も早く、林道が整備され気象や鳥獣害が少ない稀な山林です。
立木売買にたずさわっているとそれがわかります。
山林と立木の売買は全然違うことをご理解いただけたでしょうか?