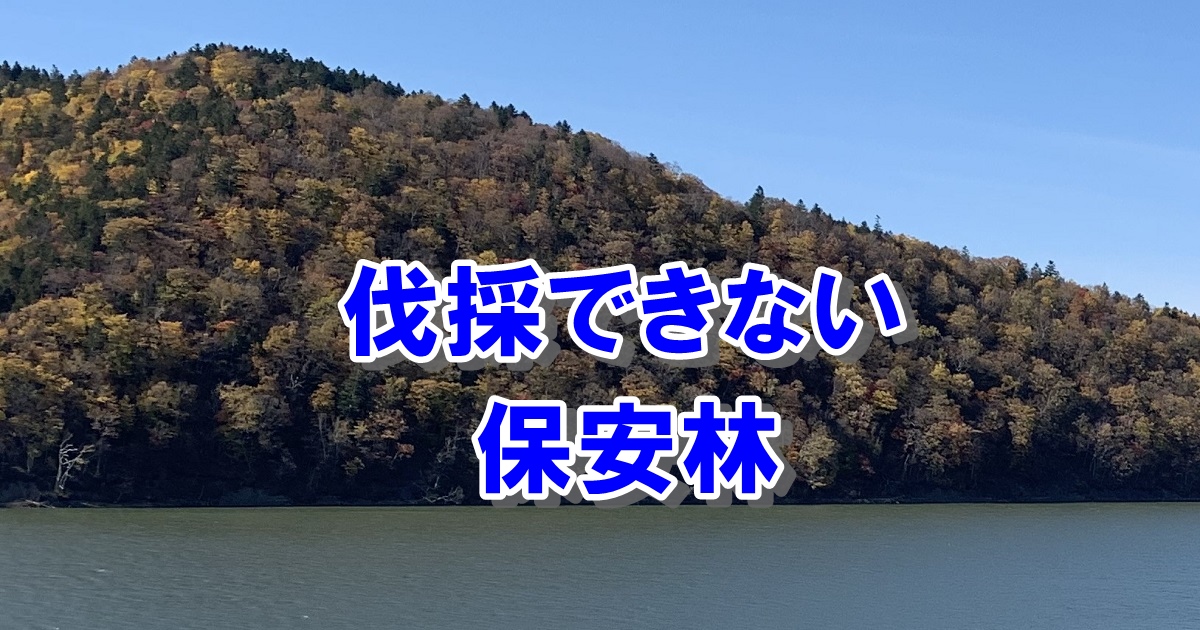人工林とは人の手で植林育林された山林をいいます。
それに対して、長い年月をかけて種から自然に自生した山林を天然林といいます。
北海道の山林面積は550万haです。
そのうち約26%が人工林で145万haです。
人工林は一般的に将来に立木を販売して利益を得るのが目的です。
収入を得るための経済林と位置付けられてます。
ところが、立木売買の相談をいただいても立木買取できないことがあります。
それは所有者でも自分の立木を伐採できない保安林に指定されている山林です。
全国の保安林は約1227万haとされています。
北海道の保安林面積は約377万haで、うち国有林が286万haです。
保安林に指定された民有林が91万haもあるのです。
なぜ、人工林なのに伐採できない?
所有する山林が保安林に指定されていることを知らずに、立木を売りたいと考える方がいます。
しかし、保安林に指定されていれば、所有者でも伐採ができません。
なぜ、自分たちの先祖が植林した人工林なのに、立木伐採して販売できないのでしょうか?
それにはまず、保安林制度を知る必要があります。
とにかく植林した影響

近年の人工林には変化がありました。
日本国内では古くから建築などで木材需要が多かったので、木材を使用する目的で植林されました。
成長が早いカラマツ、トドマツ、エゾマツなどの針葉樹が植えられました。
時が経ち、円高や海外の安価な輸入材の増加により、次第に日本国産の木材は売れなくなります。
建築構造も変化し、木造中心から鉄筋コンクリート造が増えはじめたのも影響がありました。
「どこでも植えとけば儲かる」と資産形成目的で、投機的に植林したかもしれません。
急斜面や再植栽が難しい山林でも伐採と植林が進みました。
水害や土砂災害などが増えてきてやがて保護する山林も必要になってきます。
人工林であっても危険とされる山林は伐採が制限されてます。
ずっと人の手が必要な人工林

人の手で植林した山林は完全な自然ではありません。
根の張り方や深度、密集度などで天然林とは異なります。
自然災害や保水能力など山林機能が脆弱です。
山間部は傾斜地が多く、農地の耕作放棄地のような平地でありません。
放置しておくと細い立木が倒れたり、表層土砂崩れや流木被害を発生させます。
植林したからには、育林から伐採まで一貫して人の手が必要なのです。
伐らないで保護すべき立木もある

日本の山林は急峻な地形が多いです。
多数の被災者を出し、家屋を失う水害や土砂災害を幾度も経験しています。
そんなことで江戸時代から伐木を制限する決まり(規制)がありました。
あきらかに山崩れが起きそう(すでに起きている)そんな山林もあります。
私たちが現場で見てて、「あと数年で崩れるな…」と感じる植林地も数多くあります。
そんな場所は立木を残すようにしたり、作業道をつけません。
経験を積めば現場の見た目で、将来の土砂災害をある程度は予見できます。
管理されてる国有林や公有林だけが山崩れを注意していても限界があります。
地続きの民有林が勝手に伐採を繰り返していては、総合的な山林機能が低下します。
災害防止の保安林制度

17種類の防災目的として、保安林制度があります。
土砂崩れ防止や水源涵養(雨水保水機能) などが含まれます。
個人の山林が保安林に指定されていても売買は可能です。
しかし、伐採や変更は自分の山林であっても勝手にできません。
すべての山林が営利、経済目的だと無計画な伐採で広域的に不利益を被るでしょう。
近年の巨大台風や地震災害により、人命財産が毀損するのは重大な問題です。
山林機能の回復には数十年の年月がかかります。
植林育林したり林道敷設、治山工事した資産が失われ、莫大な国家の損失になります。
豪雨に対して
保安林に指定されている面積の約70%は「水源かん養保安林」です。
約20%が「土砂流出防備保安林」です。
保安林面積の大部分が大雨などで洪水、土砂崩れを防止する目的であることが想像されます。
保安林は水害対策と言えます。
ゲリラ豪雨など過去にない異常な降水量の大雨が近年は観測されてます。
山林には保水機能の「自然のダム」の役割があります。
保安林指定は豪雨被害を最小限に食い止める機能を期待されているのです。
役割が変わってきて、求められる山林機能
人口減の日本においても木材需要は堅調にあります。
木材は住宅建材だけでなく、物流梱包資材、バイオマス発電燃料としても需要が高まってきてます。
CO2削減のために生産地が近い国産材資源を、大切に使う活動は継続されるでしょう。
これまでのように木材資材をたくさん産み出す植林地としての役割は変わります。
CO2吸収や土砂災害防止のための、公益的な機能を求められてます。
これからは保安林の対象指定範囲も広がることが予想されます。
豪雨対策だけでなく、CO2対策、台風など強風への防風林対策や、海洋資源の保護を目的とする漁業対策等もあります。
山林、森林機能に期待する声が世界的に高まっていくでしょう。
山林を所有しているが…
保安林指定の解除について制度上は可能としてます。
しかし、一度指定されると解除になる例はとても少ないです。
営利目的としての保安林解除は認められません。
かわりに保安林所有者には、固定資産税などの税制上の優遇があります。
また、保安林内の一部の立木を更新のために択伐したり、間伐することが認められるケースもあります。
重ねてですが、保安林は自己所有の山林なのに手入れや伐採ができません。
相続したり、山林売買するときに注意が必要です。
「山林所有者になった!」と思いきや、立木伐採はもちろん、手入れや立ち入りも制限されていることがあるのです。
保安林の税優遇と義務
保安林は固定資産税が非課税で、固定資産税評価額は「0」です。
不動産取得税や特別土地保有税も課税されません。
しかし、贈与税や相続税では課税対象です。
伐採の制限度合いにより30~80%の控除があるものの「保安林は無税…」ではありません。
伐採禁止の保安林でも相続すると少しは課税されることに注意してください。
相続登記義務化で
2024年4月から登記義務化がはじまります。
保安林は国内山林面積の50%、国土面積の30%を占めています。
これから相続増加社会の到来により「保安林の相続」が増えるでしょう。
自分のヤマなのに自由に伐採できない保安林制度を知っておいてください。

保安林に指定されているかわからない…
そんな時は所在する市町村の役場に問い合わせてください。
保安林所有者の責任
固定資産税などがかからない保安林でも、所有者責任があります。
保安林の森林機能が落ちないよう適切に管理する義務があるのです。
例えば、
- ごみの不法投棄をそのままにする。
- 災害による倒木や土砂崩れが起きても放置する。
- 誤伐、盗伐、他者の不法行為を黙認する。
このような行為は認められません。
伐採制限や土地開発制限があっても、保安林所有者として管理義務が発生します。
制度を理解する
税優遇がある保安林の所有は決して損ばかりではないと思います。
「永久に一本の伐採も許されない…」というわけではありません。
手入れに必要な間伐などを申請して適切と判断されれば伐採が可能です。
相続した山林は先祖代々受け継がれてきた山林であることが多いです。
相続や贈与では課税対象ですが、税優遇を受けながら所有できる珍しい財産です。
あなたの保安林によって下流の豪雨被害を防いでいるのかもしれません。
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
保安林を相続される方も出てくると思いますが、公共の利益を考えた制度であることを理解いただければと思います。