林業経営者や森林所有者は、苗木を植えて立木を育てて伐採して丸太を生産します。
木材資源の生産者として市場に商品を供給します。
丸太のもとになる立木の育成には、30年以上の長い年月をかけます。
植林してから初回の間伐まで、少なくとも20年ほどは収入がありません。
その間は育林や林道整備などで支出ばかりです。
さらに、さまざまな山林経営上のリスクを背負うことになります。
山林経営とは資源供給が収入源ですが、一方で地球環境に貢献する環境投資でもあります。
CO2排出権取引でも注目される山林資源投資について、国内ではあまり注目されません。
よくわからないまま相続して、なんとなく山林を所有している人も多数います。
近年は「空き家対策」で税制や地方条例が改正されつつあります。
所有者不明山林所有も多く、これから長い年月をかけて対策されていくと思います。
山林所有に関するリスクを明らかにしてみます。
自然によるリスク
近年は温暖化の影響で自然災害が頻繁に発生し、発生すると被害が深刻になりつつあります。
観測史上まれにみる大型台風や、豪雨、豪雪、強風などの異常気象が観測されてます。
地震や落雷、地滑り、噴火、隕石の衝突も考えられます。
天災が発生する以上、ノーリスクで山林所有はできません。
土砂崩れ

大雨や地震によって土砂崩れが発生すると、育てた木や投資した林道を失う可能性があります。
自然災害(天災)では原則的に、誰にも被害の責任を問うことができません。
しかし、現実として復旧工事には多額の費用が掛かります。
そもそも道路が無ければ山林に価値はありません。
国や自治体の復興計画に基づく復旧作業のやり方に、協力しなければならないこともあります。
場合によっては災害復旧をあきらめて、その土地での林業経営をやめなければならないこともあり得ます。
風や雪で倒れる

強風や台風で木が倒れることを、風倒(ふうとう)と言います。
伐採で倒した木ではないので、ほとんどの風倒木は幹内部にダメージがあります。
外部から見ただけでは判別できません。
異常な豪雪も枝や幹に加重をかけて、折れたり樹幹を破壊し立木を痛める原因です。
風倒や豪雪は倒れかけた木が、別の木によりかかった状態(かかり木)にします。
林業死亡事故原因で最も多い「かかり木」処理は、安全技術と時間を必要とします。
丸太価値が低くなったり搬出に多額の費用が掛かる風雪被害木は、林業経営の大きなリスクです。
虫害(細菌やウイルスも)

キクイムシを代表とする虫害は、一度発生すると広範囲で長期にわたり被害木を発生させます。
これまでも多くの種類の害虫(菌やウィルス)が確認されています。
研究が進んでいるものの、発生のメカニズムはよくわかっていないので、予防法が確立されてません。
被害が発生するとさらなる拡大を防ぐために、虫害エリアを早く全て伐採する方法がとられてます。
近年は、これまで発見されていなかった虫や菌が確認されてます。
温暖化の影響でそれらの生息域が変化してきて、新たな被害の発生源となっていることもあります。
シカの食害(獣害)

全国的に野生動物による農作物被害が拡大してます。
北海道においては、シカなどの野生動物被害が増えています。
山奥の現場に行く私達の感覚として、個体数が増えていることを実感します。
エゾシカは木の枝や葉、樹皮を食べます。
立木が食害を受けるとそこから幹への腐朽がすすみ、立ち枯れして木材として価値がなくなります。
シカ等の農業被害が深刻ですが、実は林業被害も甚大です。
その他の獣害として、ネズミの食害は古くから林業経営の大敵です。
山火事

落雷などが原因の森林火災は自然現象でもあります。
自然界で一定数は必ず発生します。
しかし、発生の多くはタバコ、焚火、野焼き、放火など人為的な原因です。
山火事が発生すると山林の資産損失が甚大です。
所有地だけではなく広範囲にわたり、市街地にまで広がる可能性もあり環境負荷も甚大です。
何十年も投資して大切にしてきた森林資源を一瞬で失うことになります。
林業従事者は、火の取り扱いを厳重にしなくてはなりません。
社会によるリスク
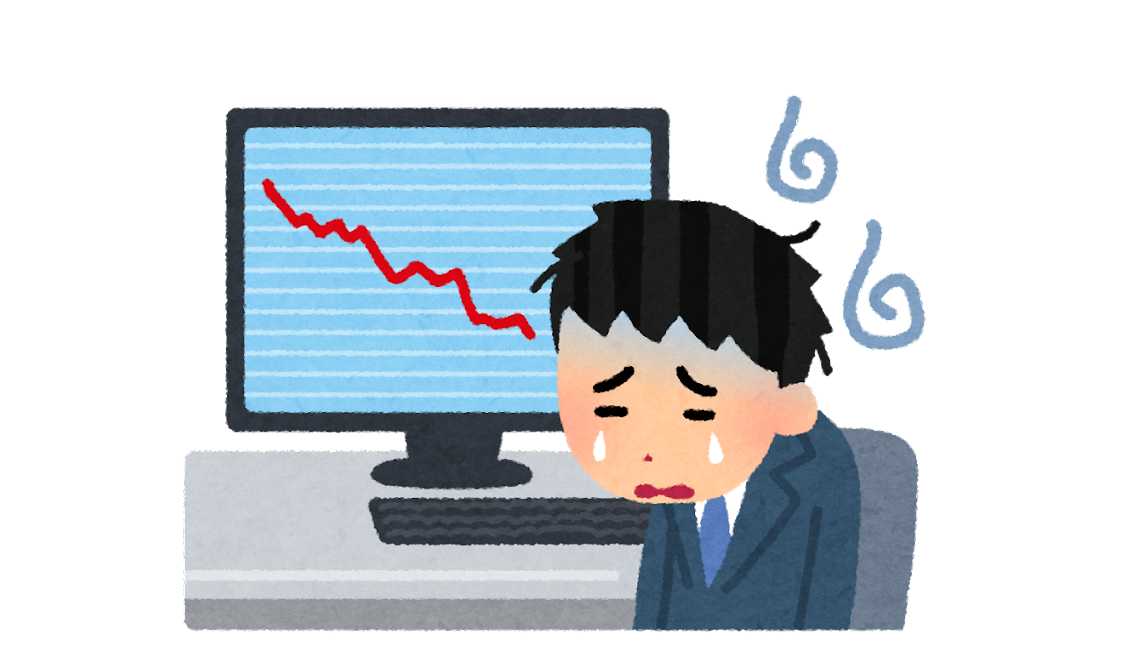
山林資源の立木は素材丸太として出荷され、市場で取引されて流通します。
景気の影響を受けて需給が変化し、木材価格は変動します。
為替動向による外国材との競争や、物流の停滞、住宅着工数も丸太価格に影響があります。
木材はバイオマス燃料として資源の側面があることも、認識しておいてください。
隣地境界がわからなくなる
山林内では大雨や雪解けで、地滑りや土砂崩れが発生します。
土砂崩れとまでいかないものの、風化による落石崩落のような小規模な土地形状変化は頻繁です。
それにより、隣地との山林境界がわからなくなることがあるのです。
林道そのものが崩落したり、河川の形状が変化するほどの災害後には、ますます境界が不明になります。
不動産取引において「境界線が不明土地」は、のちに紛争のタネとなり、価値を見出しにくい物件です。
勝手に伐採される
立木を売りたい山林所有者に案内されて現場に行くと、あるはずの立木がすべて伐採されていた事があります。
私達が実際に経験しました。
何者かが無断で勝手に他人の財産である立木を違法伐採して盗んだ犯罪です。
困難なのは現在、効果的な盗伐の予防方法が無いことです。
山林内の監視カメラ設置には、多額のコストがかかります。
深刻な農産物窃盗被害と同じことが、林業にもおきてます。
ゴミを不法投棄される

監視の眼が行き届かない山林に、ゴミを不法投棄する者もいます。
テレビや冷蔵庫などの大型家電製品や自転車、自動車部品など、様々なモノが山林に捨てられています。
何年も行かないと、建設残土やコンクリートなどの建築廃材が捨てられていたりします。
勝手に盛り土されて、地形が変わっていることもあります。
これらの処理費用は、原則的に所有者なので大きなリスクです。
山林ではこういうことが本当にあります。
丸太の取引相場の下落

グローバルに取引される現代では、丸太など木材資源も世界の相場にリンクします。
販売当時にリスクについての説明不備があったとされる国有林分収林も、過去に問題になっています。
金融ショックなどがあると、住宅販売状況や物流が悪化します。
景気減速では資源価格下落で、原材料となる木材相場も乱れます。
国内の林業経営において、植えてから伐りだすまで早くても30~40年かかります。
その時の相場を予想するのは、ほぼ不可能でしょう。
伐採時に丸太相場が下落する可能性があり得ます。
林道の整備費用の負担
隣接する山林所有者から共同で使用できる林道整備のために、費用の一部負担を求められることがあります。
共同で使用する林道は、国公有林も参画していることが多く、森林組合で扱う補助金支給もあります。
しかしながら、山林所有者の費用負担も多少発生します。
林道整備は育林、調査、伐採など、あらゆる作業で必要です。
「林道が無いと山林の価値が無い」と言っても良いくらいです。
整備費の負担は投資と考えて準備しておかなければなりません。
山林を所有するということ

環境を考える時代において、山林資源への投資は公共的な側面があります。
視野を広くすると、CO2吸収で環境へ貢献する役割があります。
SDGs(持続可能な開発目標)で、山林保護は求められる行動です。
安全資産に思える山林
しかし、農業や養殖漁業の食料資源と同じく、山林所有には様々なリスクが存在します。
山林所有も投資であり、どんな投資でも必ずリスクが存在します。
山林経営で所得を得る人がいますし、売買で損する人もいます。
何となくのイメージとして、山林所有は低リスクに思いがちです。
そこには紹介した様々なリスクがあり、決して安全資産とは言えない見方もあります。
費用と流動性
そもそもの評価額が低いので、山林にかかる固定資産税は高額ではありません。
それでも整備費負担や間伐育林などで、何かと費用負担がかかるのが山林経営です。
伐採して収入を得るまで費用がかかる一方です。
現在は少し取引が増えつつありますが、売買したいときに売り手買い手が簡単に見つかりません。
流動性が低い資産なのです。
そのため価格設定についても大きく変動することがあります。
山林所有者の充実感
以上、リスクを紹介しましたが、山林所有にはそれらを補って余りある充実感と満足感もあります。
「自分のヤマ」には立木や野生生物が存在しており、ペットを飼っているような愛着がわいてくることがあります。
休日にキャンプしたり、リラックスに訪れるのも所有山林なら自由です。
山菜を収穫したり、一部を耕してミニ農園を作ることだって可能です。
社会へ環境貢献が実感できて、知らない誰かにメリットを与えているような感覚を持つ林地所有者もいます。
祖先のほとんどが農民だった日本人にとって、林地などの土地所有は夢でした。
皆、借り地を耕して小作し、利益は地主に搾取されていたのです。
今でも山林を所有する高齢者は、代々の山林や田畑の土地を手放そうとしません。
日本人のDNAには土地を所有し続ける大義があるのかもしれません。
リスクを紹介しましたが、デメリットさえしっかり把握していれば、山林所有者は貴重な国土を管理する社会貢献者なのかもしれません。


