70年にわたり北海道で立木や丸太売買に携わってまいりました。
これまでさまざまな山林所有者や林業家にお付き合いさせていただきました。
中には何世代にもわたって管理を委託していただく山林所有者もいます。
立木の売り渡しは物品授受とは異なり取引が簡単に完結しません。
伐採後の山林資産価値を低下させる恐れもあります。
間伐して手入れをしても、その後の生長が狙いどおりにいかないこともあります。
作業道が不適切だったりすると土砂崩れがおきたりします。
知られざる立木売買取引を紹介します。
こんな買手は避けるべき…
山林売買は不動産取引で立木売買は動産の取引です。
立木の範囲、搬出期限や伐採方法などを約束して契約し、その後すぐに支払いをします。
地域により商習慣が異なっていたりします。
伐採届けが必要だったり森林組合と協議することもあります。
売買に関しては、「契約→決済→引き渡し」と通常の取引手順で問題ありません。
適切な立木売買にならずにトラブルになることもしばしば耳にします。
立木売買の専門事業者でない

一見すると所有する機械や設備は同じように見えますが、木材事業者ではないこともあります。
建設事業者であることも多くあります。
兼業とする事業者もいます。
公共事業に立木伐開という開墾のような請負事業もあります。
雑木林を伐り開くだけの仕事です。
丸太売買に精通しておらず、現在、製材工場が欲しい丸太径や長さなどのサイズを熟知していません。
立派な立木でも伐り方によって販売価格が大幅に下落します。
立木価値を最大限に引き出す能力がない事業者かもしれません。
立木売買契約書がない
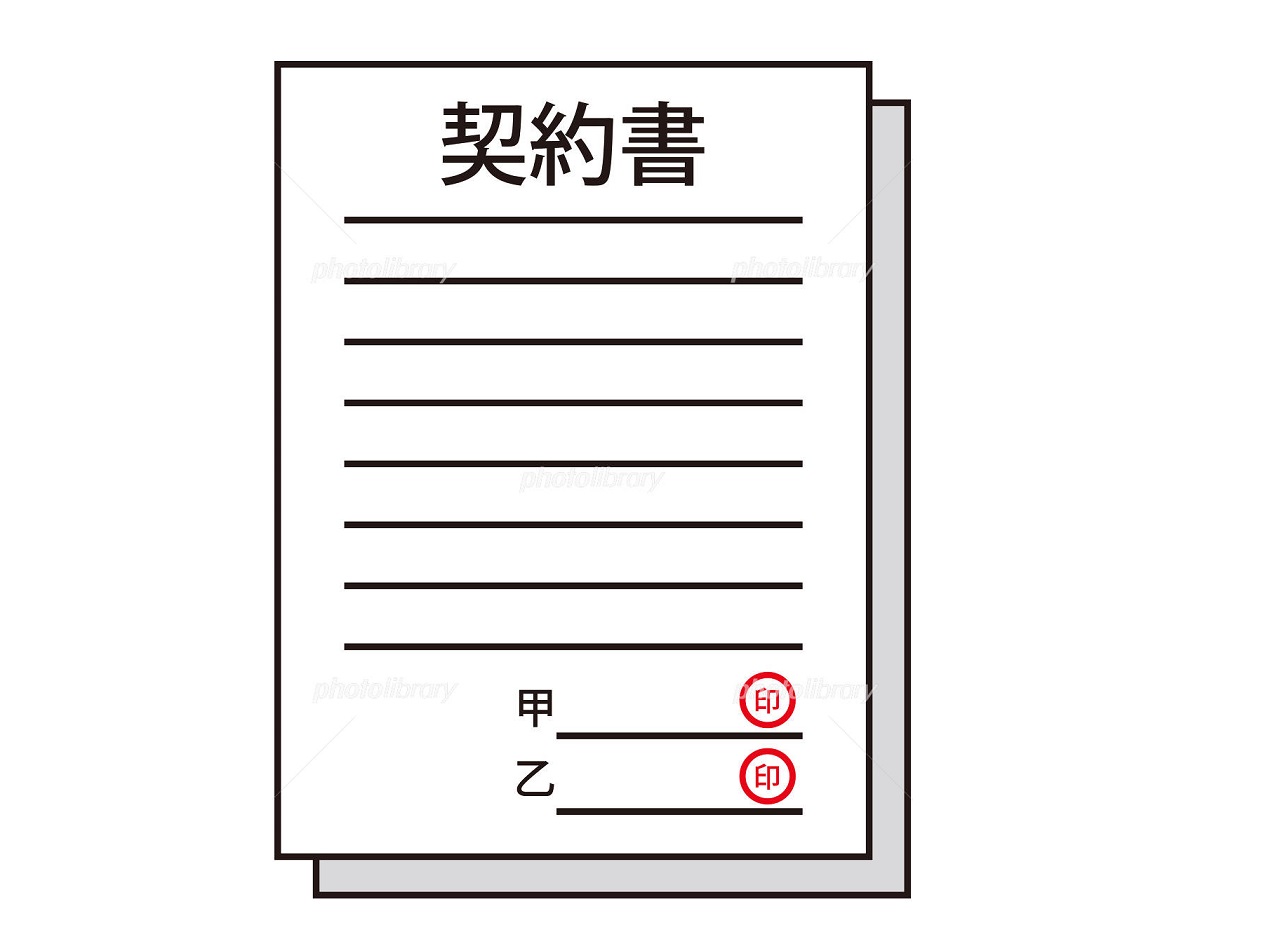
契約書を作らないという業者が未だにいるようです。
金額や契約面積などを双方合意するものの、契約書を交わさないのです。
昔の立木売買の商習慣はそうなのかもしれません。
大金が動くのに書面がないというのは、ちょっと理解できません。
約束と違う場所の立木伐採につながったり、面積、期限など条件が違うこともあり得ます。
不動産売買のように立木売買でも必ず契約書を作らなければなりません。
のちのトラブルにならないように、契約書を作らない業者と取引するのは避けましょう。
代金の支払いが遅い

契約が成立すれば、通常は買主が代金を支払います。
突然、支払日を先延ばしにされたりすることがあるそうです。
契約で約束してるのに急に支払いが遅れたりするのは、問題がある業者だと思いませんか?
支払いが伐採後や後日支払いという取引もありますが、不払いの可能性もあり売主を不安にさせます。
木材業界は手形で取引する商習慣も関係しているのかもしれません。
経営状況が悪い業者もあります。
税金の支払いもせず、実態は倒産状態の伐採業者も存在していたことがあります。
代金の支払いに関しては最大限の注意が必要です。
売買ブローカーだった

会社かと思っていたら、立木売買ブローカーだったということもあります。

契約したけど伐採業者ではなく個人だったんだよ…。
そんな相談を受けたことがあります。

その地域の立木や山林売買は、あの人が支配する…。
なんていうことも田舎にはあります。
ブローカーを通さないと立木の売買ができないような地域もあったそうです。
ただ、地域によっては現在も個人ブローカーの売買関与を聞きます。
ブローカー行為そのものは違法ではありません。
しかし、売買条件詳細を知らない伐採業者が来てトラブルが発生すると大変です。
責任の所在が明確でなく契約どおりに進まなくなることもあります。
また、事業収益が発生するので法に沿って納税しているのか確認が必要です。
トラブルに巻き込まれると余計な費用がかかったりします。
注意してください。
伐採作業現場でのトラブル
立木売買契約では搬出期限が3年というのが一般的です。
伐採作業日数が数カ月や一年かかることもあり得ます。
長い間には現場での細かいトラブルが付き物です。
契約書には金額や期限など大まかな約束事しかできていません。
危険な伐採現場で避けたいことを紹介します。
作業の安全対策ができてない
伐採現場は非常に危険で事故や災害がとても多く起こります。
林業での災害死者数は全国で年間30~40人です。
立木伐採作業は安全対策が適切かどうかが重要なポイントです。
安全教育、対策が常時おこなわれているかも大切です。
それを軽視してる木材業者が多いのも事実です。
「私の所有山林で死亡事故が発生したら…」と想像してみてください。
取り返しがつかないことになり、心理的な損害が消えることはありません。
境界を軽視、無視している

山林にも境界が必ずあり、それをよく確認しないで作業している事業者もいます。
境界を無視して伐採し、「あとから隣地所有者と話をつける…」などという信じられない業者もいたといいます。
越境しての伐採は「誤伐」と呼ばれ、損害賠償を請求されることになります。
故意に越境したりすると「盗伐」とされ、刑事上の窃盗罪で犯罪です。
林道、作業道の付け方が不適切

立木を伐り出すには道路が必要です。
伐採業者によって、林道や作業道の付け方が違います。
経験がないのにコストダウンを優先して危険な作業道、集材道を急傾斜に設置したりします。
崖上から危ない道路を付けたりします。
安全対策は、林道や作業道の付け方にでてきます。
林道や作業道の付け方は、敷設後の土砂災害を引き起こす可能性を増減する要素です。
大雨で簡単に崩れる道路もあれば、何十年も使える道路もあります。
業者が山林の将来を考えているか?注意深く見る必要があります。
コスト度外視で伐採搬出費が高騰すると結果的に立木価値を下げてしまいます。
収入減となり山林経営を圧迫します。
伐採後のことを考えて林道づくりを考える事は大切なことです。
近隣の農家から苦情が…

山林の入り口には農家が多くありトラブルを避けたいものです。
木材の運搬や振動騒音で迷惑をかけることにもなります。
伐採業者があらかじめ近隣の農家に挨拶をしているかの確認が必要です。
伐採適期をすぎた山林を見かけます。

今、伐採搬出すれば良い金額になるのに…。
過去のトラブルで近隣の農家所有農地を通行させてもらえず着手できないのです。
迂回すると莫大な搬出コストがかかるため伐採できない事例です。
隣地とトラブルが発生すると将来にわたって通行を許可してくれなかったりします。
のちのさらなるトラブルにもつながります。
せっかく価値ある山林が、過去のトラブルで隣地所有林道の通行許可が出ないのはもったいないです。
10km以上も林道新設しなければならないので費用が莫大になります。
手を付けられない優良山林はよくあります。
道路の使用許可を得ていない
他の山林所有者や市町村等の公有林の林道を通行するときは、使用許可を得なければなりません。
林道は共用道路が多く使用には届け出が必要な場合もあります。
伐採業者が適切に手続しているか確認が必要です。
伐採や搬出作業によって道路を汚したり、痛めたりすると修復する義務があります。
その責任が山林所有者にまわってくることがあります。
ゴミを捨てていく

使用したオイルや伐採機械消耗品、飲食のゴミなどを山林内に捨てていく業者もいます。
山林内にゴミを投棄していく行為は許されません。
数十年前は伐採作業中に飲酒してたり、喫煙しながら作業している業者がいたそうです。
飲酒運転はもちろん違法ですし、タバコの不始末で山火事が発生する可能性もあります。
伐採後のあとも考えて…
立木の価値を高く評価し、値段をつけてくれる業者に売り渡したいのは誰でも同じです。
しかし、高価で契約したものの近隣農家との関係がこじれてしまうと大変です。
今後の農道通行を許可してくれなくなったりすると、山林の資産価値は大きく下がります。
伐採作業では民事上のトラブル防止に努めてくれる事業者を選定すべきです。
また、事故が多い林業作業では安全対策がとりわけ重要です。
他人が引き起こした事故とはいえ所有林内で死傷されたりするのは、心理的に良いことが一つもありません。
危険な作業には必ず無理な施工計画や準備不十分があり、原因が存在します。
作業現場で災害にもろい作業道や伐採の仕方があると、のちの植林後にも土砂災害等の崩落が起きやすくなります。
間伐においてどの木を切るのかは、太い長いや売り価値だけで決められません。
事後のほかの立木の安全生育を考えなければなりません。
山林経営は長いスパンで収益を考えなければならないのです。
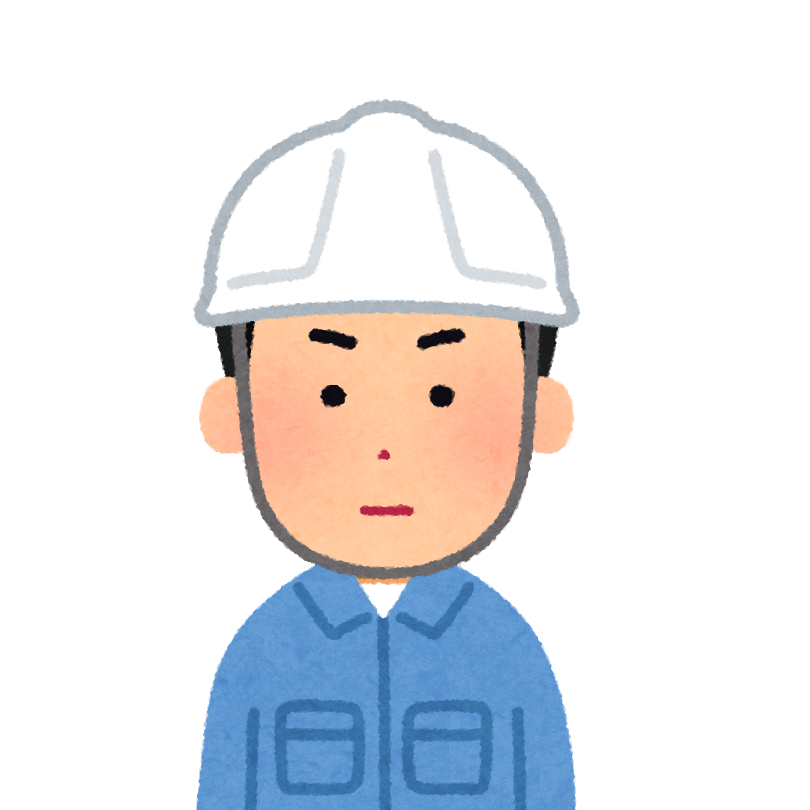
無事是名馬…。
災害に強い山林をつくれるかが、長期でみた収益の最大化につながります。



