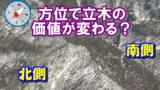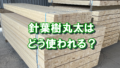人気観光地の北海道でドライブ中に皆さんが見る山林は、緑が深くて空気がきれいで大自然に映るでしょう。

うわー、北海道の広大な大自然!
でも、私たち木材業者は違う視点で山林を見てます。

生長が悪い、林道が無い…
緑を眺めているのに高価な立木だ…とか、傾斜がきつく林道がないので伐採費用が高価だ…とか思ってしまいます…。
素直に自然を楽しめない悲しい一面です…
同じように見える山林。
価値の差を決めるのは、いったい何でしょうか?
自然とは言えない経済林・生産林

林業で立木生産している山林を経済林(生産林)と呼びます。
人工林とも呼ばれます。
北海道では主にカラマツやトドマツ、アカエゾマツなどが植林されてます。
林業は、植栽して育林し価値ある立木に育ててから伐採し素材丸太に加工します。
最終的に素材丸太として販売するのが目的です。
営利目的の経済林に対して、国公立公園のように自然保護を目的とし、原則的に伐採を禁止している天然林(自然林)もあります。
人工と天然がわかりにくい山林

人工林と天然林をかりやすいように説明すると、農地と草原を想像してください。
農地は作物収穫を目的として農耕して作付けし収穫します。
パッと見ると、農地作物の緑なのか?人の手が入っていない草原の緑なのか?
これは皆さんわかりますよね?
それと一緒なのが天然林と人工林です。
でも、山林は見た目ではわかりにくいのです。
経済林の成績が良い、悪いとは?

林業経営者は「どの山林が稼げて、どの山林がイマイチ」なのかを把握しています。
稼げる山林は植林育林に投資を検討できます。
でも、稼げない山林はそれができません。
経済林の成績が良い悪いというのは「植林から伐採販売」までで稼げたかどうかです。
伐採搬出コストの格差がある

間伐(木の間引き)の本数や回数、タイミングは立木種類や状態によって違ってきます。
それによって、その山林の総売上や総出荷量が変わってきます。
また、立地(土地形状)や気候、あるいは土質や方角が重要です。
切り立った地形の立木を原木丸太にして搬出するのにはとても苦労します。
豪雪地帯は除雪が必要で林道の損傷が激しいです。
それらの費用は、搬出コストを高くしますので収益を圧迫します。
丸太品質が悪いことも
地域によっては丸太品質の欠点が発生したりします。
土質のせいなのか土地崩落が影響しているのか、はっきりと原因がわかりません。
トドマツによくある、アテやヌレと言われる丸太の欠点があると価格が安くなります。
気候も影響しているとされ、まだ、未解明なことも多いです。
主伐となった時に価値がつけられない丸太になるのはショックです。
腐朽菌やネズミ、害虫が頻繁に発生する地域があったりします。
価値ある経済林は生産性が高い

傾斜が緩く広大な面積を活かして北海道では林業者が多いとされます。
生産性を高めて搬出コストをおさえ、山林経営ができる地域もあります。
木材が大量に輸入される現代では、木材価格が昔のように大きく変動しません。
販売価格が急上昇することはあまり考えられません。
なので、搬出するコストをいかに抑えるかがポイントとなります。
丸太販売価格で植林育林、搬出コストをカバーできる山林は価値が高い経済林と言えます。
まとめ、立木の生産効率が良い山林は高価値

立木を伐り出し原木丸太にする作業の生産性を高め、コストを抑える努力が必要です。
高性能機械の導入やそれに伴う工程の見直しは、続けていく必要があります。
事故がない安全が第一です。
非効率なことをやめ、立木価値を最大限に引き出すことが求められています。
林道投資は必ず必要
しかし、それだけでは限界があります。
林道新設や補修など素材丸太生産に長期的視野で投資しないと、結局は山林の生産性を下げてしまいます。
山林経営において道路が最重要です。
林道がないと現場視察もできず、何をするにも林道がないとはじまりません。
成長した立木の価値が高くても、搬出するときのコストが高いと利益が少なくなってしまいます。
道路新設や維持に多額のコストがかかります。
経済林で利益を見込むなら長期にわたる林道投資計画が必要です。